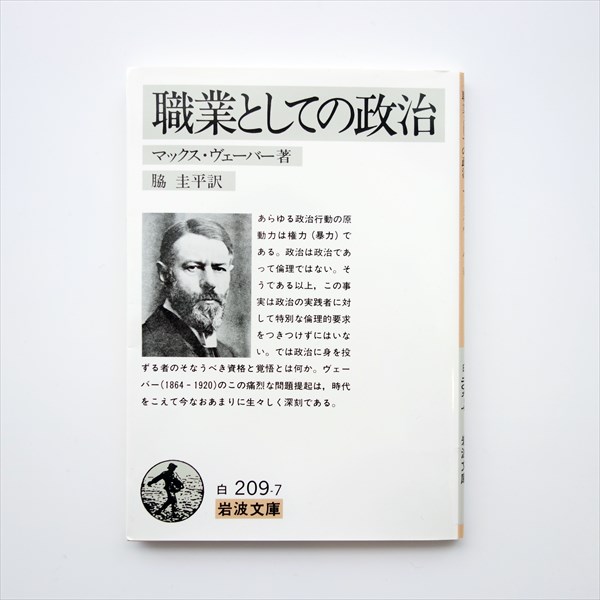あらためて言うまでもなく、来週末(10/31・日曜日)は衆議院選挙です。
どうせ自分の一票なんかで何も変わらない、だれが当選したって一緒、そんなふうにお考えの方も少なくないでしょう。
でも選挙は投票してだれかが当選してハイ終わりという単純な多数決ゲームではありません。
選ばれた議員がそれからの任期で何をしたか、だれのためにどう動いたか、そこへの絶え間ない監視とプレッシャーこそが我々個々の国民が選挙後もしなくてはならないことであり、投げやりな全面委任でも無謬性を前提とした手厚いサポートでも、ましてや個人崇拝ではないわけです。
その積み重ねなくして、真の意味での民主主義社会とは言えますまい。
もちろんこのブログでどこの党の誰に入れてくださいなんて野暮な呼びかけはしませんが、一市民の権利でありせっかくのイベント、大いに楽しみましょう。
当店では政治への参加もある種の装いのひとつと敢えて捉えており、一昨年の参議院選の際に、この時期だからこそ改めて読んでみたい、読み返したい本を3冊ご紹介致しました。
この記事が意外と読まれていたようですので、調子に乗って第二弾をお届けします。
今回も、あまりに専門的な学術書やイデオロギー色の強いものではなく、安価かつ入手が容易で比較的読みやすい、定番的な本を選びました。
1.クリストファー・R・ブラウニング/ 普通の人びと ホロコーストと第101警察予備大隊(ちくま学芸文庫)
ナチス政権下、ポーランドで38000人のユダヤ人を殺害し、45000人以上の強制輸送を実行したのが、第101警察予備大隊です。
彼らはナチス台頭以前の教育を受けた世代で、とりたて熱狂的な反ユダヤ人主義者でもなければ狂信的な政権支持者というわけではありません。
商人や職人、薬剤師など、市井に生きたおじさんたち、つまりは「普通の人びと」によって結成されていました。
そんな彼らがなぜこのような凄まじい虐殺劇の主役となったのか、そのメカニズムを解析したのがこの本です。
これは決して他人事ではななく、我々にだって起こり得ます。
ただでさえ、技能実習生問題や入管での絶えぬ虐待、関東大震災の「井戸」などを挙げるまでもなくこの国では欧米(もっといえば白人)以外の外国人に侮蔑的感情を抱く人は少なくありませんし、権力側としては人種差別や排外主義などで国民を煽動することが容易い環境にあります。
政権寄りスタンスのテレビの昼のワイドショーなんかもそんな感じで近隣の国への敵愾心を日々煽っていますし、犬笛が吹かれる準備はいつだってできています。
まじめでお上の言うことに従っていれば、多数派の論理に追随していれば「善良な市民」として穏やかに生きていけるのか、そこは常に疑っていたいですね。
決定的な要因は、集団への順応であった。大隊はユダヤ人を殺害するように命令を受けた。しかし個々人はそうではなかった。しかし80パーセントから90パーセントの隊員が、ほとんどは-少なくとも最初は-自分たちのしていることに恐怖を感じ、嫌悪感を催したが、にもかかわらず殺戮を遂行したのだった。列を離れ、一歩前に出ること、はっきりと非順応の行動をとることは、多くの隊員の理解をまったく超えていたのだった。彼らにとっては、射殺する方が容易だったのである。
2.エティエンヌ・ド・ラ・ボエシ/ 自発的隷従論(ちくま学芸文庫)
話にならないような悪政が蔓延るのは何も現代の日本だけではありません。
古今東西、いつだってそれはありふれたものでした。
しかし、権力者がいくら権力を持っていたとしても、それは数の上では少数派ですよね。
それなのになぜこのような構造が簡単に実現し、維持できてしまうのか。
16世紀のフランス、わずか18歳(16歳という説もあり)のラ・ボエシ青年がそれを考察し、まとめあげたのがこの『自発的隷従論』でした。
人が権力に隷従するのは、それを強いられているからではなく、むしろ自発的なものである、本書はそう指摘します。
それはそうなるよう環境がつくられているのもありますし。隷従によっておこぼれにあずかれるという構造が人をそうさせるわけです。
ねずみ講よろしく、まずトップの権力者に5~6人の隷従者がおり、その恩恵を受ける。その5~6人の下にそれぞれ数百人がいて、甘い汁を吸える。そしてその下に…のようなメリットこそが自発的な隷従を促します。
若者の書いたものですから、ときおり感情的に過ぎる表現や考察の雑な部分も散見されますが、それでも本筋としては的を射た、普遍的な内容だと思います。
圧制者の詐術として並べられた「遊戯/ 饗応/ 称号/ 自己演出/ 宗教心の利用」なんて、まるでどこかの島国のようではありませんか。
トルコの大王は、書物や学識というものが、ほかのいかなるもにもまして、人間に、自己を知り圧制を憎む能力を理解力を与えることを熟知している。だから彼は、自分の領土に識者をほとんど置かず、そんな連中を求めたりもしないのだ。多くの場合、時流に抗して自由への献身を守りつづけてきた人々の数がいかに多くとも、互いに知り合うことがなければ、そんな熱意と情熱も、効果をもたらさないままになるものである。圧制者のもとでは、行動や言論はおろか、思想の自由さえも完全に奪われているので、彼らのような人々でも、みな自分の考えのなかに閉じこもり、ばらばらになってしまっているのだ。
そもそも、「国家」とは何でしょう。
20世紀初頭、マックス・ヴェーバーは、現代に於けるそれを「ある一定の領域の内部で正当な物理的暴力行使の独占を(実効的に)要求する人間共同体」と定義づけました。
国家以外のすべての団体や個人に対しては、国家の側で許容した範囲内でしか、物理的暴力行使の権利が認められない、ゆえに国家こそがその行使の権利の源泉である、というわけですね。
政治というものは、どんなスケールでの話(国家間~もっと小さな集団間)であっても、個々人にとってみれば分け前にあずかるべく権力の配分関係に影響を及ぼそうとする努力そのものであり、倫理ではない。ゆえに道徳的観点からの批判は無意味である…実に身も蓋もない話ですが、いざ現実を見てみると宜なるかなと頷かざるを得ないようです。
論自体はここに留まらず、それを前提としたうえでの政治を職業とする人間の持つべき資格と覚悟を問うわけですが、そこは是非実際にお読みください。
一世紀前の本ですからもはや古典と言っても過言ではなく、またいつのものであったとしても一から百まで無謬であるなんてことはありませんから、あくまでひとつの物事の見方に過ぎないとはいえど、今もなお一読に値する書です。
政治的に重要なのは、むしろ彼らの手足となって働く補助手段の方である。政治的支配権力はどのようにして自己の支配権を主張し始めるのか。この問いはあらゆる種類の支配について、したがってどんな形態の政治的支配-伝統的支配、合法的支配、カリスマ的支配-についてもあてはまる。
どんな支配機構も、継続的な行政をおこなおうとすれば、次の二つの条件が必要である、一つはそこでの人々の行為が、おのれの権力の正当性を主張する支配者に対して、あらかじめ服従するよう方向づけられていること。第二に、支配者はいざという時には物理的暴力を行使しなければならないが、これを実行するために必要な物財が、上に述べた服従を通して、支配者の手に掌握されていること。ようするに人的な行政スタッフと物的な行政手段の二つが必要である。
投票日まではもう日もそれほど残っていませんが、それまでに読まねばとかそんな話でもありませんし、あくまできっかけとしてご紹介しただけですから、タイミングが合えばくらいの気持ちでいつかお手に取っていただければ幸甚です。